【CEOブログ】2020年を「DX元年」に掲げた企業たちは今
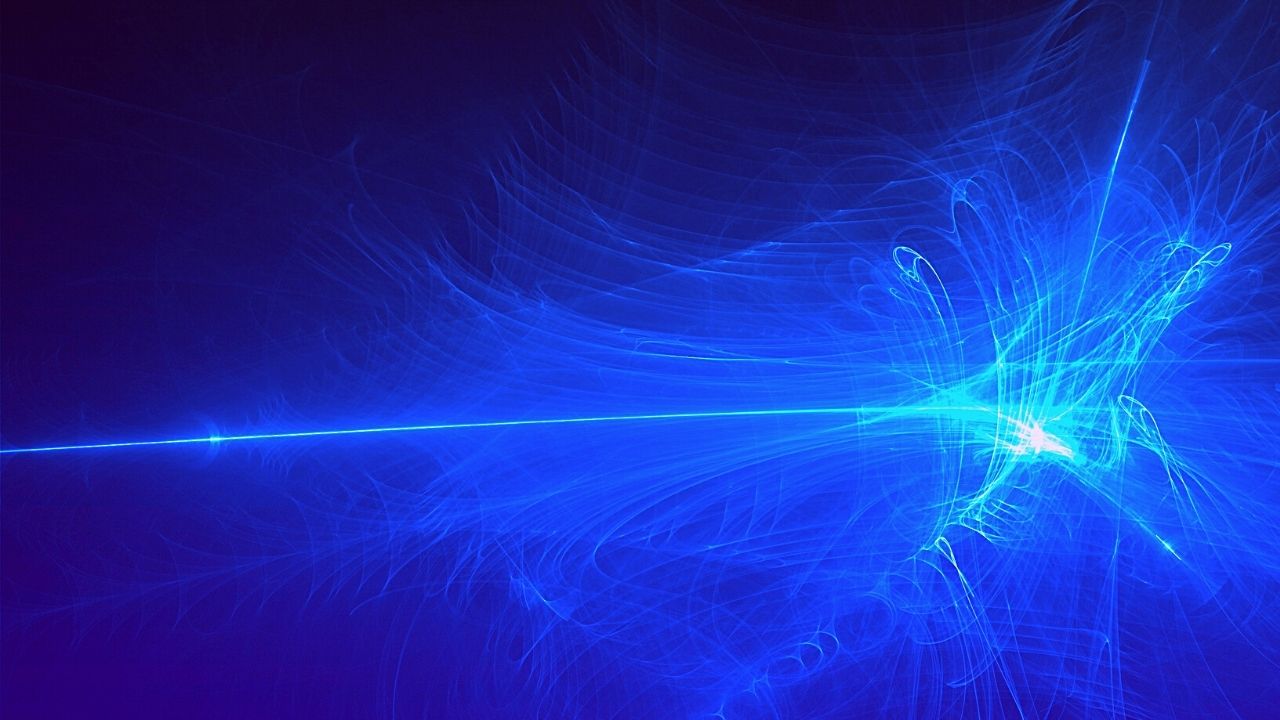
ニュースなどで毎日必ず一回は『DX(デジタル変革)』という言葉を耳にしたり、目にしたりするようになってから久しい。DXを完了させるのには3-5年ほどかかると言われるが、2020年から本格的にDXに着手している企業の中には、そろそろ折り返し地点に差し掛かろうとしているところもある。このようなタイミングを捉え、ここでは改めてDXを振り返ってみたい。「DXとは何か?」についても、おさらいの意味で本投稿の中では触れていく。
尚、昨年9月にマッキンゼーが発表した「デジタル革命の本質:日本のリーダーへのメッセージ」は、DXを取り巻く環境を丁寧に説明している。こちらの内容を念頭に、本投稿は状況把握に努めるものである。
1.時間軸
DXは2004年にスウェーデン・ウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が最初に提唱した概念である。しばらくの時を経て、2018年12月、日本では経済産業省が「DX推進ガイドライン」を発表している。
この経済産業省の発表もあってか、2019年の一年間は日本企業にとってDXに対する認識を深める期間となった。その結果、翌年に入ると「2020年を会社のDX元年」と位置付け、自社のDX取り組みを対外的に明示する企業も増えていった。
また2020年と言えば、新型コロナウイルスの影響で我々の働き方が大きく変わった一年である。これはDXの観点では、一部企業にとっては、デジタル対応を加速させる追い風となっていった。その一方で、DXの専門家を雇用し、社長直轄でタスクフォースを組成したのにも関わらず、進展がほとんど見られなかった企業もある。このように2020年の各社DX推進は、その明暗が分かれるところとなった。
2020年9月には経済同友会・櫻田謙悟代表幹事による(菅新政権に期待することへのコメントの中で)「DXは待ったなし、日本のデジタル化は3周遅れ」のコメントがあり、この発言は報道などで広く知れ渡ることとなった。これはDX対応が遅れている企業を鼓舞するメッセージとも受け取れる。
DXの完了期限は2025年と言われることがある(通称『2025年の崖』)。この頃には時代が大きく変わっていて、そこから企業が大掛かりな変革を起こすには遅すぎるという考え方である。DXに要する時間は通常3-5年ほどであるが、2025年が期限と考えると、2020年中にDXを前進させられずに2021年を迎えてしまった企業たちが焦りを感じているであろうことは、想像に難くない。
2.IT導入とDXの違い
<「当然の前提」が変わる>
我々が誰かとLINEの連絡先を交換するとき、その相手に「スマホを持っていますか?」と質問することはない。相手が当然スマホを持っていると考えるからである(厳密に言えば相手がスマホでなくてもLINE利用は可能であるが)。取引先に対して「今度オンラインでビデオ会議をやりましょう」と話をする際、「御社にはネット回線が通っていますか?」と我々が質問をすることはない。相手の会社に当然ネット回線が通っているであろうと考えるから。このように、我々の生活には数多くの「当然の前提」が存在しているが、この前提は時の経過の中で変化をし続けている。スマホも、ネット回線も、十数年前には当たり前ではなかった。
これと同様のことがビジネスモデルに関しても言える。ビジネスモデルを構築する上での「前提」は時代の中で変わっていく。今の社会には、昔に作られたビジネスモデルが多数存在しているが、時代の変化を踏まえた既存事業の見直しは必須であり、これを進めていこうとする動きこそがDXである。
<両者の違い>
社員全員にスマホを支給する、あるいはオフィスに出社することは義務付けず、ビデオ会議システムを多用しながら自宅からでも働くことができる環境を整備する、これらは「IT導入」である。ビジネスを推進する上での「手段」にデジタル化を取り入れた動きに過ぎず、別にビジネスの「目的」そのものが変わっていっている訳ではない。
一方でDXは、デジタルネイティブな社会環境下で、事業の対象者や目的も含め、「ビジネスモデルそのものを見直していこう」とするものである。そしてビジネスモデルの見直しには、社内の組織変更が伴う。また組織やビジネスモデルは会社の理念の上に成り立っていることが多いので、急進的な変化を促す場合、企業文化そのものから変えていかなければならない。DXとは、「ビジネスモデル、組織、企業文化の変革」と本質的には同義なのである。アメリカのウォールマートはDXの成功事例として取り上げられることがあるが、同社もDXを通じて「企業文化」を積極的に変えにいっている。
<誰がやるのか>
先に述べたスマホの支給や、ビデオ会議環境の整備であれば、社内のIT部門に依頼をしたり、場合によってはアウトソースしたりすることがある。ただし、ビジネスモデル、組織設計、会社の在り方(企業文化)、これらのことを考える場合、IT部門に依頼して済むものではない。DX推進の当事者は会社であり、各事業部である。DXで先行する同業他社の事例などにも学びながら、自社の経営戦略、営業部門、管理部門、これらの在り方を抜本的に問い質すところから全てが始まる。
3.どう進めるか
冒頭で触れたマッキンゼーレポートの中で、働く時間の20%をDXに充てているCEOの事例が紹介されている。これまで述べてきている通り、DXは「ビジネスモデル、組織、企業文化の改革」と同義である。CEOがコミットした上で、ある程度トップダウンで進めない限り、その実現は難しい。
またDXは会社の在り方自体を問う重要ミッションであることから、社内のエース級社員をDXチームに集結させている場合もある。DXは容易なことではなく、失敗をしたり、試行錯誤を繰り返したりの連続であるが、その過程を経て前に進むものである。社内のDX部門以外の人たちは、DX部門の動きを短期的な結果やアウトプットのみで評価するのではなく、暖かい目で見守ってあげたい。
尚、社内のDXチームが直面する最大の壁は、多くの場合、社内(=身内)からの抵抗である。DX戦略はあるが、他の社員からの理解が得られないということはよくある。変革をしなければならない理由を理解してもらえない、また何を目指すのかを理解してもらえない。加えて、求められていることを実行に移すのに十分なITスキルを備えた人材がいない。スモールスタート(小さい規模感で一旦始めてみる)で始めるも、目に見える成果が得られず、そのまま話が立ち消えしてしまうことも。だからこそ大胆に、トップダウンで、組織一丸となって一気に進めていくべきものとなる。
これまで述べてきた通り、結果は短期間で目に見えることはなく、また社員のITスキルも突如として磨かれるものではない。DXは社内の資金と人材を含むリソースを総動員した大型投資であり、3-5年継続することでようやく辿り着くことができるものである。
4.期待される効果
ここまで概念的な話をしてきたが、DXは具体的に組織に対してどのような効果をもたらすのであろうか。大きくは3つあると言われている。
1つは事業推進に関わる「効率改善」。これはデジタル利用を通じたコストカットや時間短縮によって実現される。2つ目は「顧客満足度の向上」。デジタル利用はサービスや商品に幅を持たせることに貢献する。顧客に対してはより柔軟に対応することが可能となるので、顧客に寄り添った営業ができる。そして最後3つ目は、新しい発想に基づいたビジネスモデルがもたらす「イノベーション」である。
「ビジネスモデル、組織、企業文化の改革」を念頭に置いたデジタルの利用は、ここで述べた3つのDX効果を同時に実現させていくものであり、これは定量的にしっかりビジネスの売上にも反映されていく。
+++++
電子ファイルをメールやチャットでやりとりするのが主流の時代にあって、紙の書類を郵送することでしかコミュニケーションを図れない企業は淘汰されてしまうかもしれない。リモートワークやビデオ会議が盛んな時代にあって、対面で会話をする以外の商談方法を持たない企業は淘汰されてしまうかもしれない。
これと同様に、2020年代にあって、会社としてDX対応を完了させられない企業は淘汰されてしまうかもしれない。経済同友会・櫻田謙悟代表幹事の言葉にある通り「DXは待ったなし」であり、2025年までのカウントダウンは更に続く。
#DX #デジタルトランスフォーメーション #デジタル変革
